昨年末、12月小田原市議会一般質問で何名かの議員さんから取り上げられた.こちらの懸念事項を皆さんと共有します。
なお、添付の関連資料は、記載のとおり、ある市民有志の方々からのものです。ご一読よろしくお願いいたします。
市議会での加藤憲一市長の答弁は、一旦、立ち止まって再検討する旨がありましたが、皆さん、市側の動向を注視していきましょう。
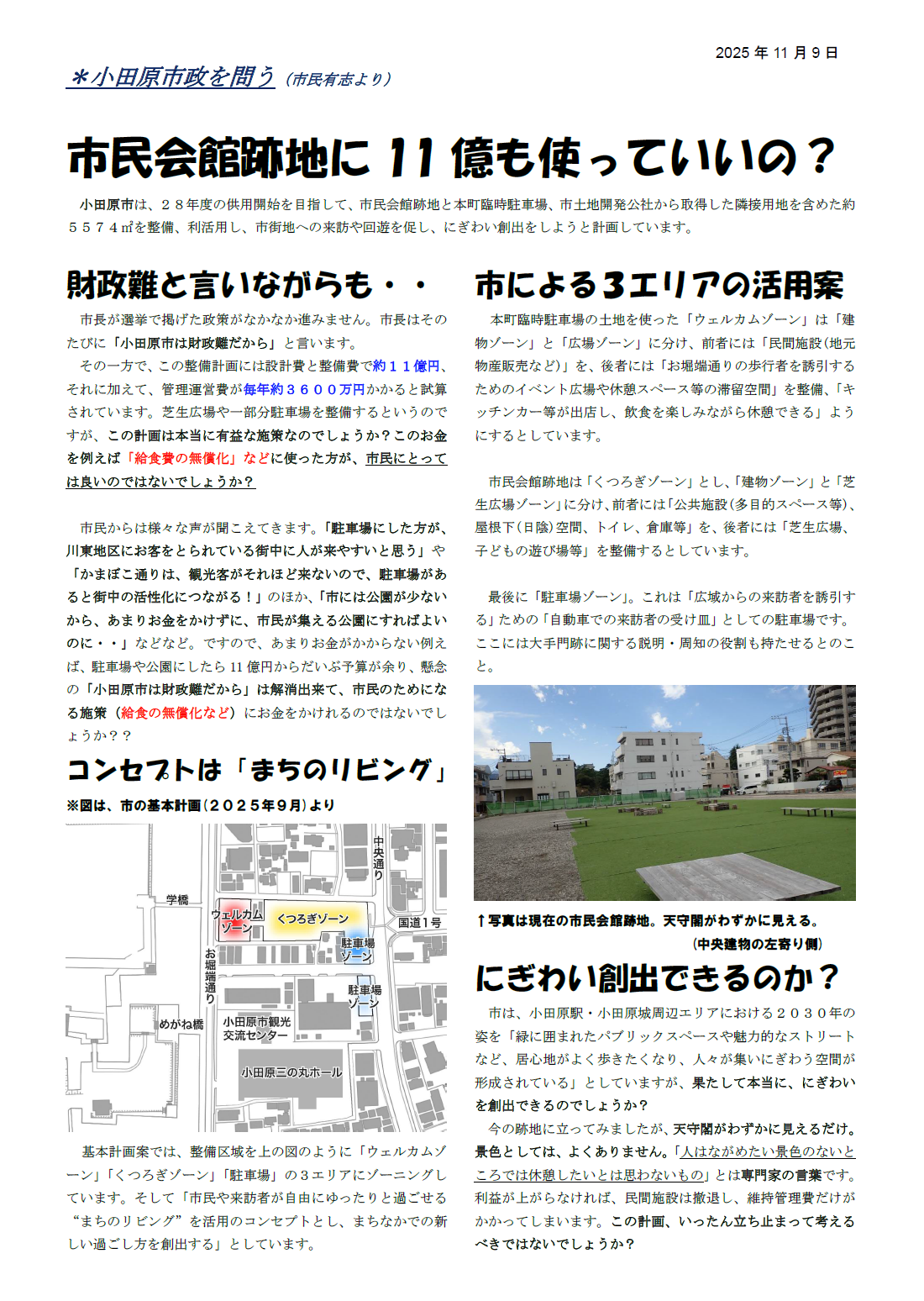
画像をクリックするとPDFファイルとして大きく表示されます。
1.小田原市で起こった自治会の「消滅」
小田原市でも、ついに「自治会が消滅する」という前例のない事態が生じました。
これまで加入率の低下や自治会役員の高齢化が課題として取り上げられてきましたが、「消滅」が起こるのはまだ先だろうという希望的観測がありました。
しかし、わたしたちの暮らす小田原で現実に消滅が起きたことは、市民にとっても行政にとっても深刻な警鐘といえるでしょう。
2.市議会答弁と小田原市の姿勢
こうした状況について、先日の小田原市6月議会では「自治会の現状は危機的ではないか、市が管理すべきではないか」との一般質問が出ました。
しかし、市側の答弁は「危機的状況とは考えておらず、その状況を市が管理するべきものではない」というものでした。
確かに自治会はあくまで地域の任意団体であり、市が直接的に統制するものではありません。
それでも行政施策とのつながりは深く、市民生活に直結する役割を担っています。
日々の活動の人手不足や財政的な厳しさを抱える自治会としては、「危機ではない」という答弁が現場感覚とずれていることは否めません。
ここにこそ、オンブズマンとして市としっかり対峙していく必要があります。
3.デジタルも活用した自治会のあり方
一方で、行政を指摘するだけでは状況は改善しません。
任意団体である自治会をどう魅力的にし、暮らしを豊かにする場へ変えていけるのか?
そのために、市民自らが動くことも求められています。
その第一歩として考えられる手段の1つがデジタル化ではないでしょうか。
東京都では、自治会や町内会のデジタル化にかかる費用を全額助成する制度が始まりました。
https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20250825/1000121074.html
電子回覧板や会費のキャッシュレス化、SNSを活用した情報共有などを導入することで、自治会役員の負担は軽減され、若い世代にも参加しやすい環境が整います。
ただし、高齢者が取り残されないよう、紙の回覧板との併用や「スマホ教室」といった補完策を合わせて運用することも欠かせません。
小田原市でも、市民と行政が協働してこうした仕組みを積極的に取り入れていく必要
があります。
4.市民にも求められる主体性と協働の姿勢
小田原で自治会消滅が現実になったという事実は重いものです。
しかし、それを契機に「新しい自治会像」を模索できるのなら、全国に先駆けた取り組みとなり得ます。
行政だけに任せるのではなく、市民が自らの暮らしを守る意識を持ち、市と協働しながら再構築を進めていく。
その姿勢こそが、自治会を再生させ、市民の安心と満足を高める道筋になるはずです。
オンブズマンとしても議論を深め、市への提言につなげていきたいと思います。
暑さ真っ盛りの7月21日(祝日)の午後に県西地域である開成町の街づくりをテーマとした、表題、開成町会議員の意見交換の場に参加して来ました。
その模様や感じたことを以下に記載致します。
*活動報告のなかに、より良い地域・街づくりへのテーマを取り上げ、開成町や町民のためにより良い街にしていきたい思いが、女性議員のソフトな語り口から如実に出ていたのが、とても良かったです。
(私も自分の地域をよりよいものにしたい思いもあり、自治会副会長や地区体育振興会の理事長などをしているところですので、議員の思いがとても伝わってきました)
*報告会のなかで盛んに出た「足柄」という地域の名前(南足柄市、開成町、大井町、松田町、山北町、中井町の1市5町)は、私は小田原市民なので、日頃、意識もなく、その名前も使わないなのですが、「足柄」地区みなさんで頑張って地域連携している様子は、せっかくなので、2市8町の県西地域全体へともっと広げていく事が大事だと思いました。
(私見ですが、政治的なところをふくめ、足柄下郡と足柄上群は地域意識の融合性に欠けている。県西中心役の小田原市が取り持っているとは言い難い印象でありますので・・)
*ではなぜ、県西地域全体での地域連携が大事かと言いますと, 政治、経済産業やスポーツ、受験生の勉強・受験やそのほか何でも、レベル的にはなかなか勝てない横浜(及び、川崎)が目立って中心となっている神奈川県のなかで、、
自然豊かや気候が安定していて住みやすいとか、箱根・湯河原等の観光地があるとか、人と人とのつながりが温かいなどとかの、良い特異性について県西地域全体が、もっともっと県内に知れ渡るよう、PRしていくべきだと改めて感じました。
*そのためには、勝手ながらの思いですが、いまこそ小田原高校の出身者同士でもあり、世代が近い加藤憲一小田原市長と山神裕開成町長がその意識をもたれ、進めていったら良いはずだと思うところです。
*「足柄」地区(1市5町)は、そのような連携感の雰囲気が報告会全体のなかで伝わりました。
出席議員さんも、南足柄市の議員、松田町の議員、開成町の議員、山北町の議員が会場にいらしてたのも象徴されていると思ったところです。
(松田町の議員さんからは、新松田駅北口地区周辺整備による駅前再開発の状況が参考情報として話題に出ました。)
ですので、「足柄」から「県西」全体へと自治体・地域連携が発展し、横浜や川崎の方々から
「神奈川に県西もあり!」のイメージにぜひともなって欲しいと思います。ご利用ありがとうございます。
旧ページからご利用の皆様には、ページの配置、構成について大幅に変更されております。
あらためてご案内申し上げます。
旧ページでは、メニューの「会員ブログ」をクリックしてください、とアナウンスしておりましたが、手間なく、はじめから新しい記事をお読みいただけるように、このサイトにアクセスした際、はじめに最新の記事が表示されるように致しました。
旧ページの機能も、ページをスクロールしていただき最下部に、日付別のアーカイブと
目次に当たるカテゴリーをご用意いたしましたので、お役立ていただけますと幸いです。
2025年8月10日 開成町 無所属女性議員の 活動報告会にて、今後の開成町街づくりについての意見交換の場に参加して(2025.7.21)
2025年5月7日 会員ブログに、南足柄市「令和7年度議会報告会」を拝聴して
(2025.5.3記)を掲載致しました。
2025年1月8日 会員ブログに、小田原市職員措置請求に係る検査の結果について(通知)、
公文書存否応答拒否決定処分に対する審査請求について(答申)
を、それぞれ掲載致しました。
2024年11月17日 会員ブログに、「続報」 「小田原市の政治倫理規定に関する申し立て書」 を小田原市議会および、同議会事務局に提出しました。
を掲載致しました。
2024年10月25日 会員ブログに、「小田原市清閑亭の問題に関係して」
「神奈川新聞社から取材インタビュー」「参議院議員 水野もと子氏と懇談会」
「開成町、山上町長へ就任二年目のインタビュー」をそれぞれ掲載致しました。
2024年9月6日 (カテゴリー)会員ブログに「返り咲き 加藤憲一小田原市長との懇談会」を掲載いたしました。
(カテゴリー)活動予定に、2024年10月開成町町長を訪問、を追記いたしました。
2024年8月9日 (カテゴリー)会員ブログに「小田原市議会模様 2024年6月議会」を掲載致しました。
2024年8月7日 (カテゴリー)会員ブログに「小田原市の政治倫理規定に関する申し立て書」 を小田原市議会および、同 議会事務局に提出」を掲載いたしました。
2024年6月16日 会員ブログに6月23日投票の湯河原町長選挙について掲載致しました。
2024年6月8日 年度定期総会および会員意見交換会を実施いたしました。
2024年5月22日 会員ブログに、5月19日投開票の小田原市長選挙の結果と所感を掲載いたしました。
2024年4月5日 会員ブログに、3月24日投開票の湯河原町議選挙結果の所感を掲載致しました。
2024年3月13日 会員ブログに、直近の選挙予定を掲載致しました。
2024年3月9日 会員ブログより、真鶴町の問題を振り返って~を掲載いたしました。
2024年2月16日 会員ブログより、オンブズマン岡崎が2月1日掲載の開成町議会模様に続きまして同じく昨年12月の議会模様として、大井町の議場にも足を運びましたので、その模様を掲載いたしました。
2024年2月12日 会員ブログより、湯河原町居住の県西オンブズマンが3月24日に行われる湯河原町議会議員選挙について所感を掲載いたしました。
2024年2月1日 会員ブログより、オンブズマン岡崎が開成町12月町議会の一般質問を傍聴して来ました。 その模様を掲載いたしました。
2024年1月1日 会員ブログより、「小田原市企画「デジタルスタンプラリー」業者プロポーザル公募要項」についてが閲覧できます。
2023年11月30日 会員ブログより、県西オンブズマンが行った「小田原市政治倫理に関する問い合わせ」についてが閲覧できます。
2023年9月7日 会員ブログより「統一教会アンケート結果」が閲覧出来ます。
2023年8月30日 本年開催総会において組織概要の規約を改定しました。会員ブログから記事がお読みいただけます。
(2023年9月5日 表題、文中において文言を訂正しました。)
2023年8月7日 会員ブログに記事を4本追加しました。
前例のないコロナ禍という大変な状況にありますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
新型コロナウイルスは私たちに多大なる負の影響を与えた一方で、国の行政や政治家の想像以上の脆弱さを如実に示してくれました。
そうした状況を考えると、私たちのくらしとさらに直結している基礎自治体の政治・行政への期待は一層大きくならざるを得ません。
しかしながら現状は政治とくらしの関係性が広く一般に認識されているとは言い難く、このまま手をこまねいていてはいけないという思いが強くなりました。
そこでこうした現状を変革すべく、「県西オンブズマン」を立ち上げました。